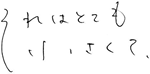むかしむかし、といっても大人になってからだけど、小さな姉妹とおともだちだった。
姉妹は、当時私が働いていたパン屋さんに週末のたびやってきて、店の隅っこでお絵かきしたり、店の前でなわ跳びしたり、していた。
お客さんがいないときに歌ったり踊ったりしていたこともあった。
妹のユリは絵が上手で人懐っこく、いつも愉快なことを言ったりやったりしたくてたまらないようだった。
お姉ちゃんのうしろをくっついてまわり、すぐ真似しては、すぐ飽きていた。
姉のマリは字が得意で人見知り、もじもじとうつむいて、はにかんで、そろっと手をつないでくる。
お母さんが毎日言ってるであろうその言い方で、「はーしーらーなーいー」と妹に注意していた。
3回めか4回めの週末、マリが小さな声で「おともだちになって」と言った。
ユリは「おともだちじゃないの」と言った。
私は「おともだちだよ」と言った。
そのように私たちはお互いをおともだちとして認め合ったのだ。
あるときユリが夜空に浮かぶ大きな月を描いていて、そのまんまるな黄色には、重ねて描かれたウサギの顔があった。
それで私はずっと疑問だったことを聞いてみた。
「ねえ、ホントに月にウサギが見える?」と。
「私にはくたびれたおっさんが見えるんだけど」と。
それから慌てて「疲れたおじさん」と言い直した。
マリは首をかしげて「わかんない」と言った。
ユリは「おっさん!おっさん!」とはしゃいでいた。
私は内心しまったなあと思いつつ、「こんなふう」としょんぼりしたおっさんの横顔を描いてユリにわたした。
翌週、姉妹は走ってやってきて、ユリが折りたたんで持っていた私の絵を広げ、「おっさんいたよ!」と報告してくれた。
ふたりはただのおともだちではなく、後にも先にもただふたりだけの、「月におっさん」説の賛同者だった。
パン屋で働く最後の日、姉妹はなかなか顔を出さなかった。
夕方になって姉妹のお母さんがやってきた。
お母さんは、今まで本当にありがとうねとおじぎをして、手紙をくれた。
そして少し困った顔で、車まで来てもらえないかな、と言った。
店長に断ってからお母さんについていくと、車には眠りこけているユリと、真っ赤な目をしたマリがいた。
車まで歩きながらお母さんに聞いた。
今日は街で花を買ってから3人でパン屋に来る予定だったこと。
でも川沿いにたくさんの野花が咲いていて、マリが「この花がいい」と言ったので、姉妹で花を摘んだこと。
パン屋へ向かう車中、上機嫌だったマリがどんどん無口になり、着いても車から降りようとせず泣いていたこと。
「おなか痛いの」と心配していたユリも寝てしまい、途方に暮れたお母さんが私を呼びにきてくれたこと。
「いっぱい遊んでくれてありがとう、楽しかったね」とウサギのようなマリに言った。
「お花摘んでくれたの?」と聞くと、背中に隠し持っていたしおしおの花束を差し出してくれた。
まるでこの世の終わりのような顔で。
そのとき、なぜだか自分が小さな女の子になったような気がして、とても胸が苦しかった。
今でも思い出すと苦しい。
そしてそのあと、自分が何と言ったのかがどうしてもわからない。
ありがとうは、ちゃんと笑顔で言えたのだろうか。
ユリは目を覚ましたんだっけ。
ずっと強く握られていた花束の茎の、その生温かさだけが手によみがえってくる。
*
天袋の整理をしていて見つけた手紙を読んで、どうにも後ろめたい気持ちになりました。
もうずいぶん長いこと、ふたりを忘れていたから。
ユリの手紙には「またあそuでね」、マリの手紙には「ずっとわすれないからね」と書いてありました。
月におっさん、今もいるかな。
次の満月の夜に確かめてみるよ。